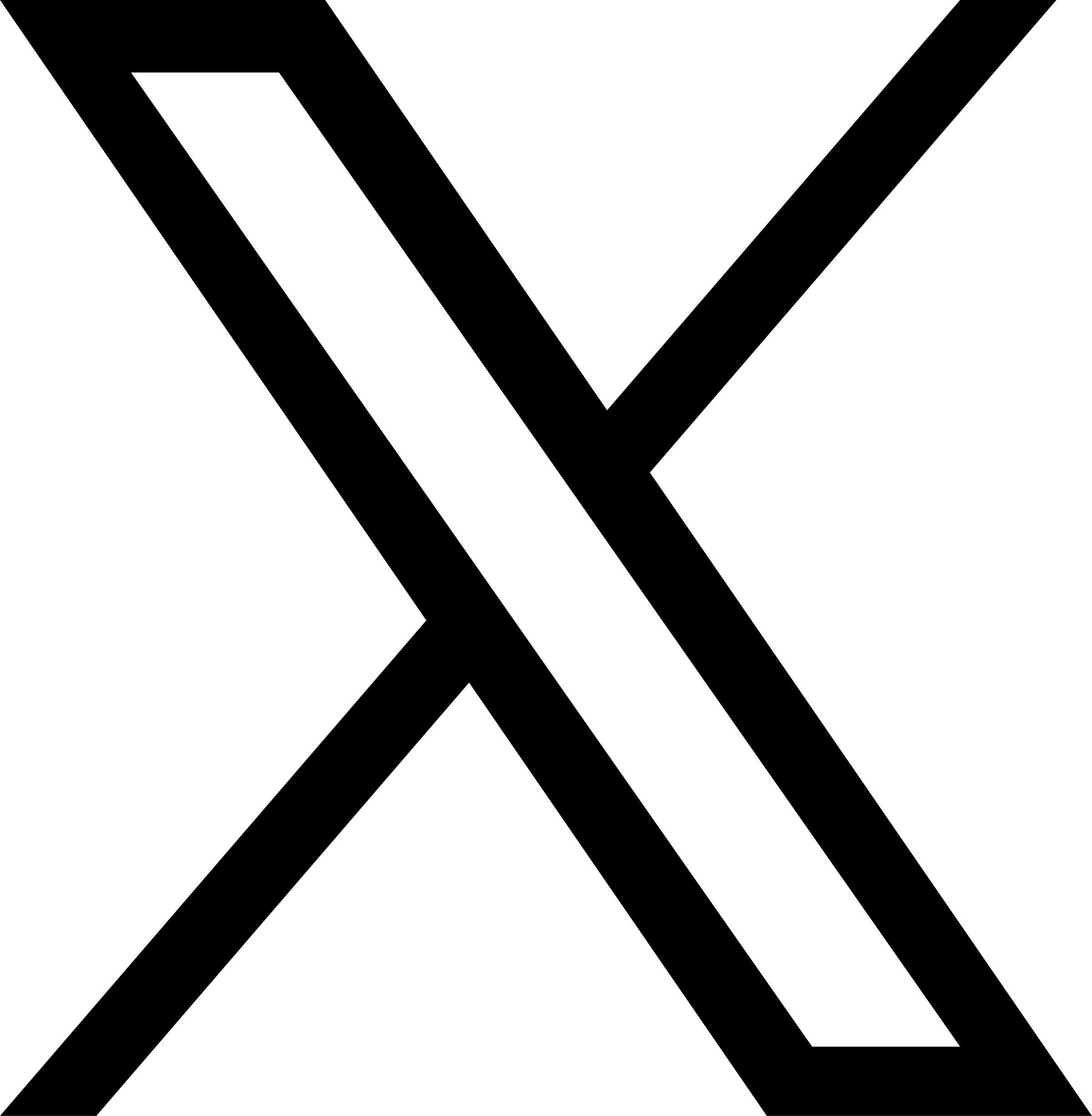こんにちは!
先日の記事では、一般の方向けにPHR(パーソナル・ヘルス・レコード)についてご紹介しました。
今回は医療現場での活用に焦点を当ててご紹介します。診療やケアの現場でPHRがどのように役立つのか、医療従事者の方向けに具体的に解説します。
1. はじめに:情報の断絶が生む『医療の課題』とは?
重複検査と投薬 : 他院検査や処方は”ブラックボックス”
現在の医療の現場では、各クリニックごと、薬局ごとにそれぞれの個人の情報を管理しています。他院からの処方はお薬手帳を見るまでわからず、お薬手帳の持参がなけれは使用薬剤を把握することはとても困難なのが現状です。
また、医療機関によって検査歴や治療歴の管理がバラバラ。
このため、つい先日に行った採血項目と全く同じ検査を他科で行ってしまったり、既往歴から必要な検査項目が不足してしまうことも。
自己申告頼りの既往歴:申告内容と服薬情報が一致しない!?
夜間帯や緊急時の受診先で病歴聴取を行う際は、患者さま本人の自己申告で情報を得るほかなく、特にご高齢の患者さまや、小児患者さんの付き添いを頼まれた祖父母からは正確な情報が得られない場合が多いです。
医療連携時のタイムラグ:その紹介状、最新ですか?
転院時などに欠かせない「診療情報提供書」
できれば患者さまの最新情報を記載したいところですが、転院のタイミングによっては必ずしも最新のものではない可能性があります。急性期の頻繁な処方内容変更等のに対応するのも大変ですが、慢性期の患者さまで、情報の更新が少ない場合こそ反映漏れが起こるケースも。
このような医療現場で実際に起こる、様々な問題を解決する方法の一つがPHRサービスです。
2. PHRとは?医療者にとっての意味
PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)を簡単に言うと 『患者さま個人の健康情報を患者さん本人のもとで管理するしくみ』です。
健康診断の結果、 あらゆる医療機関の通院履歴、 使用している薬剤、過去の使用薬、 ワクチン接種歴、 体重、バイタルサイン、歩数など、患者さまのあらゆる「体」に関する情報を1つの場所にまとめて記録・確認できる、患者さま自身が持ち歩く「カルテ」のようなものです。
PHRを管理できるサービスには様々なものがあり、私たちが提供する「harmoワクチンケア」も予防接種情報を管理できるPHRサービスのひとつです。
PHRの活用がもたらす医療者側のメリットとしては、
- 他院通院歴や処方薬がオンタイムでわかる
- 自宅血圧を含む通常時のバイタルサインがわかる
- 検診時の結果を確認できる
- 予防接種歴がわかり接種スケジュールを立てやすい
- 生活習慣病などの治療生活をサポートしやすい
などが挙げられます。
患者さまご本人がデータを持ち歩いているため、治療歴等の把握がスピーディー。適切な診断や治療開始にがつながる可能性があります。
3. 現場での活用事例 : 医療者の“困った”をPHRで解決
PHRは、すでに現場で効果を上げ始めている実践的な仕組みです。 ここでは、具体的な活用イメージをご紹介します。
事例①:病院外来 × PHR = 重複処方を防止
課題
・紹介状がなく、患者さまの既往歴が不明
・患者さま本人に聞いても「何の薬を飲んでいるか分からない」と言われる
PHRでの解決
患者さまのPHRアプリに前医での処方歴が漏れなく保存されており、医師が診察時にすぐに情報を確認可能。重複処方も防止できる。
事例②:健診・生活習慣病管理 × PHR=効果的な保健指導
課題
・定期健診のデータが紙のままで活用されず、保健指導も一時的なものに
・患者さま自身が「自分ごと」として生活改善に取り組みにくい
PHRでの解決
健診結果・血圧・体重・食事記録などをPHRアプリで“見える化”。グラフで変化を視覚的にとらえることで、自分の健康状態を客観的に把握できるように。 保健師・看護師の支援も、個々の記録に基づいたパーソナライズされた指導が可能になり、患者さまの主体的な取り組みを後押し。
事例③:病院職員のワクチン接種管理 × PHR=接種漏れゼロへ
課題
・医療従事者に接種が推奨されている、B型肝炎ワクチンや麻しん・風しんワクチンの接種履歴の確認に手間がかかる
・抗体価の把握や、接種が不足している職員の抽出が困難
PHRでの解決
医療従事者個人のPHRアプリに、接種履歴(ワクチン名、接種日)や抗体価を記録し、管理チームと共有。管理側は自動で一覧化された接種状況を把握でき、接種不足は自動で判定。本人もアプリで状況を確認できるので、接種漏れを防げる。
PHRは“患者の生活”と“医療現場”をつなぐツール
PHRは単なるデジタルデータではなく、「患者さまの背景や意思も含めて見える化するインフラ」です。病院や診療所だけでなく、在宅・訪問・介護・避難所など、あらゆるケアの現場で活用されています。
4. よくある疑問Q&A〜セキュリティは?費用は?導入の手間は?〜
PHRって便利そうだけど、実際の現場では「どう使うの?」「よくわからない…」という不安もあるかもしれません。ここでは、医療機関でよくある質問にお答えします。
Q1:セキュリティとプライバシーは大丈夫?
A:マイナポータルや医療系アプリは、国の基準や高いセキュリティ対策のもとで運営しているため、安心してお使いいただけます。
Q2:費用がかかるのでは?
A:患者さま用のPHRアプリの多くは基本機能が無料です。ただし、患者さまの情報を医療機関のパソコン等で参照できるサービスは有料の場合があります。詳細は各サービスの提供会社にお問い合わせいただくと安心です。
Q3:こういったアプリの導入を決め、患者さまに持ってもらう場合、医療者負担がむしろ増えるのでは?
A:最初は「アプリの説明」などで少し時間がかかるかもしれませんが、一度導入すれば、問診がスムーズになったり情報の聞き間違いが減るというメリットがあります。
Q4:スマホを持っていない人はどうするの?
A:タブレット貸出や、病院の専用端末で見る仕組みを用意しているケースもあります。また、アプリによっては家族のスマホに連携することも可能です。
5. まとめ:PHRは“患者中心の医療”への第一歩
「患者中心の医療」という言葉が重視されるようになり久しいですが、PHRはその実現を支える「現場で使える仕組み」の一つです。
これまでの医療現場では、医療機関が管理していた患者さまの情報は医療機関が変わる度に情報が断絶し、医療の重複や情報不足の原因となっていました。PHRを利用することで、患者さまが自分自身で健康情報を管理し必要なときに必要な場所に共有することが可能になり、診療の効率化と医療の質向上に繋がります。
医療は患者さま一人ひとりの人生に寄り添う仕事です。患者さまの健康情報を尊重した医療の実現に向けて、PHR活用の場が広がっています。
「harmoワクチンケア」も、PHRを活かして、患者さまと医療がよりスムーズにつながる環境づくりに挑戦しています。